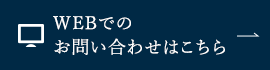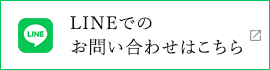近年、働き方の多様化に伴って、企業やフリーランスとの間で「業務委託」という取引形態が急増しています。
しかし、その一方で、契約内容が曖昧なまま取引を進めてしまったため、「言った・言わない。」の水掛け論や、報酬の未払い、知的財産権の帰属を巡る紛争が後を絶ちません。
こうしたトラブルを未然に防ぎ、双方が安心して取引を行うためには、実態に即した業務委託契約書の作成が不可欠です。
そこで、本記事では、上場企業のインハウスローヤー(企業内弁護士)として、年間で数百を超える各種契約書の作成・レビューを行い、企業法務の最前線で活躍している弁護士が、≪業務委託契約書の基本構成≫・≪注意すべきポイント≫、そして≪法的な留意点≫を解説します。
ぜひ、最後までご確認ください。

目次
業務委託契約書の作成に関する重要性 |
業務委託契約書は、取引の基本ルールを明文化し、当事者双方の権利義務を明確にするため、重要な文書です。
口頭での合意だけでは、後日、「言った・言わない。」の水掛け論になりがちです。そこで、契約書を作成することによって、以下のようなメリットが享受できます。
| ①紛争予防 | 契約内容を明確にすることで、将来的なトラブルを未然に防ぎます。 |
| ②権利保護 | 自社の権利(知的財産権、対価請求権など)を法的に保護します。 |
| ③法的効力 | 契約内容に違反があった場合、法的な根拠に基づき損害賠償などを請求できます。 |
| ④信頼関係の構築 | 誠実な契約書作成は、取引先との信頼関係を築く第一歩となります。 |
業務委託契約書の基本構成 |
業務委託契約書は、主に次の項目で構成されます。これらの項目を漏れなく、かつ具体的に記載することが大切です。
| ①表題 | 「業務委託契約書」など、契約内容が分かるように記載します。 |
| ②当事者 | 委託元と受託元の名称、住所、代表者名などを正確に記載します。 |
| ③目的 | どのような目的で契約を締結するのかを簡潔に記載します。 |
| ④業務内容 | 最も重要な項目です。後述します。 |
| ⑤委託料(報酬) | 報酬額・支払方法・支払時期などを明確に記載します。 |
| ⑥契約期間 |
いつからいつまで契約が有効なのかを記載します。 |
| ⑦機密保持義務 | 業務上知り得た情報の取り扱いについて定めます。 |
| ⑧知的財産権の帰属 | 業務を通じて生み出された成果物の知的財産権が、どちらに帰属するのかを定めます。 |
| ⑨損害賠償 | 契約違反があった場合の損害賠償について定めます。 |
| ⑩再委託 | 受託者が第三者に業務を再委託できるかどうかを定めます。 |
| ⑪解除 | 契約を解除できる条件を定めます。 |
| ⑫反社会的勢力の排除 | 双方の当事者が反社会的勢力と関係がないことを確認します。 |
| ⑬協議事項 | 契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の協議方法を定めます。 |
| ⑭合意管轄 | 訴訟になった場合にどこの裁判所で争うかを定めます。 |
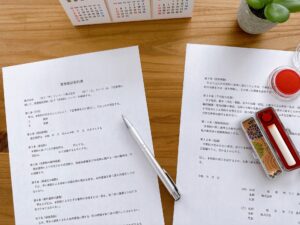
失敗しないための重要ポイント |
上記の基本構成を踏まえて、特にトラブルとなりやすいポイントについて、具体的に解説します。
【ポイント1】 業務内容を「具体的に・詳細に」記載する |
「マーケティング業務」や「システム開発」といった漠然とした記載は、避けるべきです。
【例】
| NG例 | 「SNSマーケティング業務」 |
| OK例 | 「X(旧:Twitter)およびInstagramにおける投稿作成、フォロワーとのコミュニケーション、月次レポート作成」 |
|
【なぜ重要なのか?】 |
|
| 認識の齟齬を防ぐ | 委託元と受託元で「業務内容」に対する認識が異なると、成果物の品質や範囲を巡って、トラブルになります。 |
| 追加業務の定義 |
契約書に記載のない業務を委託元が依頼してきた場合、それが「追加業務」であると明確に判断できます。したがって、追加報酬の交渉がスムーズになります。 |
【ポイント2】報酬体系を定義する |
報酬は、単に金額を記載するだけでなく、以下の点を明確に定める必要があります。
| ①支払方法 | 振込、手渡しなど。 |
| ②支払時期 | 毎月末日締め翌月末日払い、成果物納品後30日以内など。 |
| ③支払条件 | 成果物の検収完了をもって、支払い義務が生じるかなど。 |
| ④源泉徴収の有無 | 委託元が源泉徴収を行う場合、その旨を記載。 |
注意が特に必要なのが「検収」のプロセスです。
検収期間や検収不合格の場合の対応(再制作・修正など)を定めておかないと、検収がいつまでも完了せず、報酬の支払いが遅れるリスクがあります。
【ポイント3】知的財産権の帰属を明確に定める |
業務委託契約において、知的財産権の帰属は最も争いになりやすい点の1つです。
| 基本原則 | 成果物の著作権は、原則として、それを作成した受託者に帰属します。 |
| 例外 (契約による変更) |
しかし、業務委託契約書に「本契約に基づき受託者が作成した成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、その作成時に委託元に帰属するものとする」といった規定を設けることで、例外的として、委託元に帰属させることができます。 |
| 著作人格権 の取り扱い |
著作者が持つ「公表権」・「氏名表示権」・「同一性保持権」といった権利(著作人格権)は、譲渡することができません。このため、契約書に「受託者は著作者人格権を行使しない。」といった条項を入れることもあります。 |
【ポイント4】契約の解除条件を具体的に記載する |
契約解除の条件が曖昧だと、安易な解除や、不当解除を招く可能性があります。
【例】
| NG例 | 「当事者の一方が本契約に違反した場合、他方は本契約を解除できる。」 |
| OK例 | 「当事者の一方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反が是正されない場合、他方は本契約を解除することができる。」 |
※無催告解除:支払いの遅延、差押え、破産手続き開始の申し立てなど、重大な契約違反が発生した場合には、催告をせずに直ちに契約を解除できる旨の条項を設けることもあります。
【ポイント5】損害賠償の範囲を定める |
損害賠償の条項は、予期せぬ多額の賠償リスクを回避するために重要です。
【例】
| 「本契約の債務不履行により相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する。」といった規定だけでは、賠償額が無限に拡大するリスクがあります。 そこで、特に受託者側では、「本契約に基づく損害賠償の額は、本契約に基づき委託者が受託者に支払うべき直近3ヶ月間の委託料を上限とする。」といった形で、上限を設けることも有効です。 |
業務委託契約書の作成時における法的留意点 |
業務委託契約書の作成にあたっては、民法をはじめとする法的知識が不可欠です。以下では、特に注意すべき点を挙げます。
【留意点1】 準委任か請負か? |
業務委託契約は、大きく分けて「準委任契約」と「請負契約」の2種類に分類されます。
| 準委任契約 | 事務処理を委託する契約(例:医師への治療依頼)。「成果物の完成」ではなく、「業務の遂行」自体が目的となります。 |
| 請負契約 |
仕事の完成を目的とする契約(例:システム開発、建築、デザイン制作)。「成果物の完成」が求められます。 |
|
【なぜこの違いが重要か?】 |
|
| 報酬の支払い | 請負契約では、成果物が完成しなければ、原則として報酬を請求できません。一方、準委任契約では、業務の遂行自体に対して報酬が発生します。 |
| 善管注意義務 | 準委任契約の受託者には、善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)が課されます。 |
【留意点2】 労働法との関係 |
業務委託契約は、雇用契約ではありません。そのため、労働基準法は適用されず、最低賃金・残業代・有給休暇といった保護は受けられません。
しかし、形式的に「業務委託契約」であっても、実態として、以下のような状況にあると、労働契約とみなされる可能性があります。
| 指揮命令関係 | 委託元が受託者に対して、業務遂行方法や時間、場所などを細かく指示している。 |
| 専属性 | 委託元への業務が、受託者の収入の大部分を占めている。 |
| 報酬の性格 | 業務の成果ではなく、労働時間に応じて報酬が支払われている。 |
実質的に労働契約であると判断された場合、委託元は、未払いの残業代や社会保険料の遡及徴収といった、予期せぬリスクを負うことになります。
したがって、業務委託契約を締結する際は、指揮命令関係が生じないよう、業務内容の指示を必要最小限にとどめることが重要です。
【留意点3】 印紙税 |
契約実態が仕事の完成に対して報酬が支払われる「請負契約」であると判断される場合、印紙税の課税対象となり得ます。
そのため、契約書を締結する場合には、事前に契約内容を精査したうえで、印紙の要否を判断する必要があります(ただし、電子契約書の場合には、収入印紙が不要です。)。
|
「電子契約書」に関する詳細な解説は、「紙の契約とどう違う?電子契約書の効力と企業が得られるメリット」もご確認ください。 |
まとめ |
業務委託契約書は、単なる文書ではありません。当事者双方の権利と義務を明確にし、ビジネスを円滑に進めるための羅針盤となるものです。
本記事で解説したポイントと留意点を踏まえ、ビジネスに合わせた、具体的かつ明確な契約書を作成することが、将来的なトラブルを未然に防ぎ、健全な取引関係を築くうえで不可欠です。
業務内容、報酬、知的財産権の帰属については、後々の紛争の中心となりやすいため、専門家である弁護士に相談し、ビジネスモデルに合わせた契約書を作成することをお勧めします。
湊第一法律事務所は、これまで多数の契約書を取り扱い、また実際の紛争にも対応してきた経験から、トラブルを未然に防ぐための実務的な視点を踏まえたサポートを提供しています。経験に基づいた確かな知見で、貴社の事業を守り抜きますので、安心してご相談ください。
経験豊富な弁護士による的確な助言を通じて、安心して取引に臨めるよう全力でサポートいたしますので、契約書に関する疑問があれば、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

投稿日:2025年8月25日
【この記事の監修弁護士】
 |
弁護士 佐藤 駿介 依頼者一人ひとりに真摯に向き合い、丁寧かつ的確な対応で信頼を集める弁護士。 |
<略歴>
埼玉県出身。早稲田大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)に在学中、司法試験予備試験に合格し、続けて司法試験にも合格。
エンタメ系上場企業の法務部にて企業内弁護士として勤務し、契約書レビューや労働法務、社内コンプライアンス体制の整備など企業法務全般を担当。また、都内大手法律事務所に所属していた時期から、企業法務に加えて、離婚・不貞などの男女問題や不動産に関する法的トラブルにも数多く携わる。
現在は、湊第一法律事務所の代表弁護士として、企業・個人問わず法的支援を提供するほか、自ら設立した法人の取締役も務めるなど、実務と経営の双方に精通している。
<主な取扱分野>
・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
・債権回収
・男女問題(離婚・不貞慰謝料など)
・不動産トラブル(賃料問題・建物明渡し・不動産売買に関する紛争など)