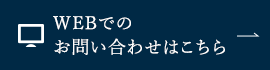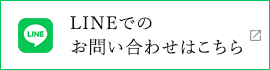企業間における継続的な取引では、「取引基本契約」と「個別契約」の存在が欠かせません。いずれも企業間取引の基盤を支える重要な契約形式です。
両者は一見似ているようで、実は役割も適用範囲も異なります。
取引の効率化に役立つ一方で、この違いを正しく理解しないまま契約を進めると、支払条件の不一致や納期トラブル、紛争時の混乱など、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
そこで、本記事では、上場企業にてインハウスローヤー(企業内弁護士)として、企業法務の最前線で活躍してきた弁護士が、≪それぞれの契約の特徴や役割≫・≪優先順位のルール≫、そして≪安全な取引を実現するためのポイント≫を解説します。 目次

取引基本契約とは |
「取引基本契約」とは、特定の取引先との間で、継続的に発生するであろう個々の取引に対し、共通して適用される基本的なルールを定めたものとなります。
この契約には、以下のような、取引全体に共通する重要な事項が盛り込まれるのが通常です。
| ①取引の基本原則 | 注文方法や納品方法、検査方法など |
| ②代金の支払い条件 | 支払期日や決済方法 |
| ③知的財産権の取り扱い | 秘密保持義務など |
| ④損害賠償 | 債務不履行や瑕疵担保責任に関する規定 |
| ⑤紛争解決 | 裁判管轄の合意など |
この契約を締結する意義は、個々の取引を行うたびに、これらの基本的な事項を交渉する必要がなくなるため、取引の効率化とスピードアップを図れる点にあります。
個別契約とは |
一方で、「個別契約」とは、取引基本契約を前提として、特定の取引ごとに発生する具体的な内容を定めたものとなります。
個別契約には、以下のように、その都度変わる具体的な取引内容が記載されます。
| ①取引の対象物 | 具体的な商品名やサービス内容 |
| ②数量 | 個数や回数 |
| ③価格 | 単価や総額 |
| ④納期・履行日 | 納品日やサービス提供期間 |
個別契約は、通常、「発注書」や「注文書」といった様々な形式で成立することが多いです。
どちらが優先される? 運用のポイント |
「取引基本契約」と「個別契約」の関係で、最も重要なのは、「どちらが優先して適用されるか」という点になります。
原則として、個別契約は、取引基本契約の内容を補完する性格を有するため、個別契約で定めのない事項は、すべて取引基本契約の規定が適用されることになります。
しかし、個別契約において「取引基本契約と異なる定めをする。」と明記されている場合には、個別契約の内容が優先されます。これは、個別契約がその取引に特化した、より新しい合意といえるからです。
例えば、基本契約で「代金の支払いは月末締め、翌月末払い」と定めていたとしても、個別契約で「今回の取引に限り、代金は納品後3日以内に支払う」と記載されていれば、個別契約で規定されている定めが優先されます。
この両契約の関係性を曖昧にしたまま取引を続けると、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
| 取引基本契約の形骸化 | 現場での個別契約によって、取引基本契約で定めた条件が勝手に変更されてしまう。 |
| 契約条件の不統一 | 個別契約ごとに異なる条件が設定され、契約管理が複雑になる。 |
| トラブル発生時の混乱 | どちらの契約が適用されるのか分からず、紛争解決が難航する。 |

トラブルを未然に防ぐためのチェックポイント |
先ほどまでに説明したリスクを回避するためには、以下の点に注意することが重要です。
① 契約適用の優先関係の明確化 |
取引基本契約書に「個別契約が優先する事項を限定する」旨の条項を盛り込みましょう。
例えば、「取引基本契約書の〇〇という条項は、いかなる場合でも個別契約は優先適用されない」と明記することで、重要な条件が勝手に変更されるのを防ぐことができます。
② 個別契約の承認フロー整備 |
現場担当者の判断だけで重要な条件を変更しないよう、社内での承認・決裁フローを確立しましょう。
例えば、一定金額以上の取引や重要な条件の変更には、社内の法務部門や部門責任者の承認を必須とするルールを設けることが有効です。
③ 契約内容の整合性確保 |
発注書や注文書などの個別契約が、取引基本契約の内容と矛盾しないか、常に確認しましょう。
契約全体での整合性を保つことが、安定した取引関係を維持するうえで不可欠となります。
まとめ |
取引基本契約と個別契約は、企業間取引を円滑かつ安全に進めるための土台です。
もっとも、契約は「結んで終わり」ではなく、「適切に運用してこそ価値を発揮する」ものです。
両者の違いと優先順位を正しく理解し、社内の運用ルールを整えることで、不要なトラブルを防ぎ、安定した取引関係を築くことができるのです。
もっとも、日常の事業活動に加えて、様々な契約書の作成やレビュー、契約管理には想像以上の時間と手間が生じる可能性があります。
湊第一法律事務所では、企業法務に精通した弁護士が、取引基本契約や個別契約の設計や優先関係の明確化をはじめ、企業活動に伴う契約上のリスク管理を徹底支援いたします。
全国どこからでもオンラインでのご相談が対応可能です。契約実務の不安や疑問があれば、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
投稿日:2025年8月15日
更新日:2025年8月17日
【この記事の監修弁護士】
 |
弁護士 佐藤 駿介 依頼者一人ひとりに真摯に向き合い、丁寧かつ的確な対応で信頼を集める弁護士。 |
<略歴>
埼玉県出身。早稲田大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)に在学中、司法試験予備試験に合格し、続けて司法試験にも合格。
エンタメ系上場企業の法務部にて企業内弁護士として勤務し、契約書レビューや労働法務、社内コンプライアンス体制の整備など企業法務全般を担当。また、都内大手法律事務所に所属していた時期から、企業法務に加えて、離婚・不貞などの男女問題や不動産に関する法的トラブルにも数多く携わる。
現在は、湊第一法律事務所の代表弁護士として、企業・個人問わず法的支援を提供するほか、自ら設立した法人の取締役も務めるなど、実務と経営の双方に精通している。
<主な取扱分野>
・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
・債権回収
・男女問題(離婚・不貞慰謝料など)
・不動産トラブル(賃料問題・建物明渡し・不動産売買に関する紛争など)