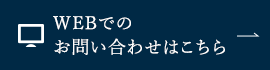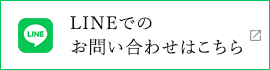企業活動において、売掛金などの債権は、資金繰りの基盤となる重要な財産です。
しかし、取引先の不誠実な対応や資金繰りの悪化によって、支払いが滞るケースは少なくありません。そして、未回収が長期化すれば、自社のキャッシュフローが悪化し、最悪の場合には、連鎖倒産に至るリスクすらあります。
このような状況に陥ったとき、最終的には、訴訟(裁判)を起こし判決を得たうえで、強制執行の実施によって、債権を回収することとなります。
しかし、裁判には時間がかかります。一般的に、訴訟を起こしてから判決が出るまでに1年以上を要することも珍しくありません(最高裁判所事務総局(令和7年7月)『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書』・「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」参照)。
その間に、債務者が不動産を売却してしまったり、預金を使い果たしてしまったりしては、勝訴判決をせっかく得たとしても、回収すべき財産がなくなり、勝訴判決が「絵に描いた餅」となってしまいます。
このような最悪の事態を回避するために有効となるのが、「民事保全手続き(仮差押え)」です。
そこで、本記事では、債権回収の確実性を高めるための法的手段である「民事保全手続き」について、多様な債権回収の案件・手続きの経験を有する弁護士が、≪民事保全手続きの概要≫から≪具体的な手続きの流れ≫まで、詳しく解説します。

目次
民事保全とは? — 勝訴判決を無駄にしないために — |
民事保全の手続きとは、裁判の結論である判決が出る前に、債務者の財産を暫定的に凍結・確保しておくための手続きを意味します。
この手続きの最大の特徴は、「迅速性」と「密行性」にあります。
申立てから保全命令の発令までの一連の手続きが非常にスピーディーであり、また、債務者側に知られることなく手続きを進めることができます。
これによって、債務者が財産を隠したり、処分したりする時間的猶予を与えず、その資産を「保全」することが可能となります。
特に、売掛金などの金銭債権回収の場面で、債務者にめぼしい資産(不動産、預貯金、他の会社に対する売掛金など)があることが判明しているにもかかわらず、支払の拒否がされているケースでは、民事保全手続きの実施を検討するべきです。
悠長に交渉や訴訟準備をしている間に、虎の子の資産が失われてしまうリスクを回避するため、金額の多寡に応じて、民事保全を視野に入れることが債権回収のセオリーといえます。

民事保全で可能なこと — 財産を「仮に」差し押さえる — |
民事保全の手続きには、いくつかの種類がありますが、企業の債権回収の場面で主に利用されるのが「仮差押え(かりさしおさえ)」です。
仮差押えとは、金銭債権の回収を確実にするために、裁判所の命令によって、相手方(債務者)が特定の財産を自由に処分できないようにする手続きを意味します。
これによって、債権者は、将来の強制執行の対象となる財産を確保することができます。
仮差押えの対象となる財産は、多岐にわたりますが、代表的なものは次のとおりです。
|
|
|
この仮差押えの手続きによって、債務者の資産を凍結し、その結果、債権回収に向けた交渉のテーブルに着かせる強力な動機付けを与えることもできます。
もっとも、仮差押えの内容によっては、債務者のメインバンクや取引先に知られ、債務者の経営に重大な影響を及ぼすことがあるため、仮差押えの対象は、慎重に検討する必要があります。
民事保全を成功させるための2つの要件 |
このように強力な効果を持つ民事保全手続きですが、裁判所は、簡単に認めてくれるわけではありません。
民事保全の命令を裁判所から得るためには、裁判所に対して、次の2つの要件を満たしていることを、証拠に基づいて、説得力をもって説明する必要があります(民事保全法13条1項)。
|
①被保全権利の存在 |
|
②保全の必要性 |
① 被保全権利の存在 — 「請求する権利が確かにある」こと — |
「被保全権利」とは、分かりやすく言えば、保全(仮差押え)によって守られるべき権利そのもの、例えば、「相手方に対して、売掛金〇〇円を請求する権利」のことを意味します。
裁判所は、そのような守るべき権利が本当に存在するのかを慎重に判断します。
そのため、申立ての際には、権利の存在を裏付ける客観的な証拠資料をきちんと揃えることが極めて重要となります(民事保全法13条2項)。
【被保全権利を疎明するための資料例】
|
|
|
|
|
これらの資料が不足していると、権利の存在自体が疑わしいと判断され、申立てが認められない可能性も出てきます。
そのため、日頃から契約書等の取引に関する書類をきちんと整備し、証拠となる書類を整理・保管しておくことが、いざという時に身を助けることに繋がります。
|
上記資料例の「取引基本契約書」と「個別契約書」の詳細は、「企業間取引の基礎知識|取引基本契約と個別契約の仕組みとリスク管理」をご確認ください。 |
② 保全の必要性 — 「今すぐ保全しないと手遅れになる」こと — |
「保全の必要性」とは、「このタイミングで仮差押えをしておかなければ、将来、たとえ裁判で勝訴判決を得たとしても、強制執行が不可能になるか、著しく困難になるおそれがある」という事情のことです(民事保全法13条1項、同法20条1項)。
裁判所は、権利の存在が認められるとしても、「裁判の決着を待たずに、なぜ、わざわざ債務者の財産を拘束する必要があるのか。」を厳しく審査します。
【保全の必要性が認められやすい事情の例】
|
|
|
|
|
|
これらの事情を説得力をもって主張するためには、債務者との交渉経過を記録しておくことが非常に重要です。
「今、保全をしないと債権回収が著しく困難になる。」という具体的な事情を整理し、裁判官に納得してもらうことが、民事保全を成功させるためのカギとなります。
民事保全に要する費用(担保金について) |
民事保全の手続きは、あくまで暫定的なものであり、本番の裁判で申立人(債権者)が敗訴する可能性もゼロではありません。もし、不当な仮差押えによって相手方(債務者)が損害を被った場合、その損害を賠償するための備えが必要となります。
そのために裁判所に納めるお金が「担保金」となります(民事保全法14条1項)。
担保金の額は、裁判官が事案の性質、請求金額(被保全権利の額)、疎明の程度などを総合的に考慮して決定します。
明確な基準は公表されておりませんが、一般的には請求金額の10~30%が目安とされています(司法研修所編『民事弁護教材 改訂 民事保全 補正版』参照)。
例えば、1000万円の売掛金を保全するため、不動産を仮差押えする場合、100万円から300万円程度の担保金が必要となる可能性があります。
ただし、これはあくまで目安です。
被保全権利の存在が契約書などで明らかであり、また保全の必要性も高いと判断された場合には、担保金の額が低くなる傾向にあります。逆に、証拠がやや不十分で権利関係に争いの余地が大きいと判断されれば、高額になることもあります。
事案によって大きく異なるため、具体的な見通しについては、事前に弁護士へご相談されるのが良いでしょう。
この担保金は、事件が終了すれば原則として、取戻しが可能です。例えば、本番の訴訟で勝訴したり、相手方との間で和解が成立したりした場合には、所定の手続きを経て返還されます。
しかし、注意すべき点もあります。万が一、本番の裁判で敗訴するなどして、相手方(債務者)から「不当な仮差押えで損害を受けた。」として、損害賠償請求訴訟を起こされ、その請求が認められた場合、この担保金から相手方の損害が賠償されることになります。
その場合、担保金の全部または一部が取戻しできなくなるリスクがあることも理解しておく必要があります。
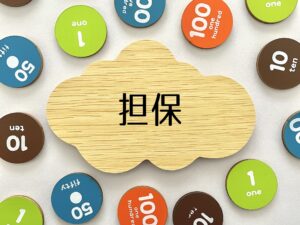
民事保全命令の発令までの流れ |
民事保全の手続きは、時間との勝負です。
弁護士による債権回収のケースにおける一般的な流れは、次のとおりとなります。
① 弁護士へのご相談 |
まずは、債権回収の見通しや民事保全の必要性について、弁護士にご相談ください。
ご相談の際、契約書などの関係資料をお持ちいただけると、より具体的なアドバイスが可能となります。
② 資料の準備 |
弁護士と打ち合わせのうえで、前述した「被保全権利」と「保全の必要性」を疎明するための証拠資料を収集・整理します。
③ 保全申立 |
弁護士が申立書を作成し、証拠資料と共に管轄裁判所に提出します(民事保全法11条、同法12条)。
この申立ては、債務者に知られずに行われます。
④ 裁判官との面接 |
申立て後、多くの場合で、申立人側弁護士が裁判官と面接を行います。
この面接の場で、申立書の内容について、裁判官から質問を受け、また口頭で補充説明を行います。事案の緊急性や保全の必要性を直接アピールする重要な機会となります。
⑤ 担保金の決定 |
面接の結果、裁判官が保全を認める心証を得た場合、「〇〇円を担保として立てることを条件に保全命令を発令する」という旨の「担保決定」が出されます。
⑥ 担保金の供託 |
決定された担保金を、法務局に現金で納付(供託)します。
なお、事案によっては、銀行等の金融機関との間で保証契約を結び、保証書を提出することで現金の供託に代える「ボンド方式(支払保証委託契約)」を利用できる場合もあります。
⑦ 保全命令の発令 |
供託が完了すると、それを受けて裁判所が正式に「仮差押命令」を発令します。
発令後、対象となる金融機関や不動産を管轄する法務局へ、裁判所から命令書が直ちに送達され、財産の凍結が実行されます。
ここまでの一連の流れは、事案にもよりますが、ご相談から発令まで1~2週間程度という迅速さで進むことも少なくありません。

まとめ |
今回は、企業の債権回収における強力な武器となる民事保全(仮差押え)について、解説しました。
もし、「取引先に十分な資産があるはずなのに、理由を何かとつけて支払いを渋っている。」・「このままでは財産を隠匿されてしまう危険性が高い。」といった状況にあれば、民事保全手続きは非常に有効な選択肢となります。
債務者の資産を凍結することで、それ以上の財産散逸を防ぎ、交渉を有利に進めるための強力なカードを手にすることができます。一方で、要件の該当性判断や担保金のリスク、迅速かつ的確な申立てなど、専門的な知識と経験が不可欠な手続きでもあります。
債権回収は、「スピード」と「戦略」が何よりも重要です。
湊第一法律事務所では、企業法務・債権回収に精通した弁護士が、迅速かつ実務的な対応で、貴社の大切な債権を守ります。
売掛金の回収でお悩みの経営者様・ご担当者様は、手遅れになる前に、ぜひ一度、湊第一法律事務所にご相談ください。状況を的確に分析し、民事保全を含めた最適な解決策をご提案いたします。
投稿日:2025年8月27日
【この記事の監修弁護士】
 |
弁護士 嶋村 昂彦 都内大手事務所および地域密着型の事務所で培った幅広い経験を活かし、企業・個人を問わず、多様な案件に柔軟かつ丁寧に対応。 |
<略歴>
栃木県出身。早稲田大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。
都内大手法律事務所および横浜市内の法律事務所で実務経験を積む。
中小企業法務をはじめ、相続(遺産分割・遺留分・遺言書作成・相続放棄など)・成年後見業務・債務整理などの幅広い個人法務に携わる。
また、神奈川県弁護士会所属時には、犯罪被害者支援委員会に在籍し、犯罪被害者支援といった公益活動にも注力する。
現在は、湊第一法律事務所パートナー弁護士として、企業・個人の双方に対し、信頼と安心をもたらす法的支援を提供するため邁進する。
<主な取扱分野>
・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
・相続問題(遺産分割・遺留分・遺言書作成・相続放棄など)
・労働事件(労使双方)
・債権回収