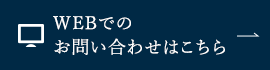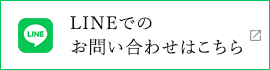相続財産の中に不動産が含まれていた場合、その評価額をめぐって、相続人どうしの意見が食い違うことは決して珍しくありません。

例えば、同じ土地を評価するのに「3000万円」と見積もる人もいれば、「1800万円」と見積もる人もいます。
そして、その差が、遺産分割で取得できる最終的な額に数百万円単位の差へとつながることも—。
このように、相続した不動産の評価額ひとつで、最終的な取り分が大きく変わってしまう可能性があるため、どのように評価するかは、遺産分割の成否を左右する重要な問題といえます。
しかし、不動産の評価方法は、法律で一律に定められておらず、複数の方法から選択する必要があります。
では、どのような方法を選べば、公平な分割が実現できるのでしょうか?
本記事では、遺産分割や遺留分、遺言書の作成など相続問題に精通する弁護士が、≪不動産の主な評価方法≫と≪それぞれのメリット・デメリット≫、さらに≪遺産分割を行うための実務的ポイント≫を解説します。
目次
相続した不動産の評価が重要となる理由 |

相続した遺産の中に不動産がある場合、公平な遺産分割を実現するため、不動産の時価を適正に評価することが重要となります。
不動産の時価は、預貯金の金額のように明確なものではありません。そのため、時価をいくらと見積もるかによって、遺産の分け方が変わってくることがあるのです。
次のケースで考えてみましょう。
|
〇亡くなった方(被相続人):父 〇遺産:㋐自宅、㋑預貯金(2,000万円) 〇分割の希望:長男は㋐自宅を、次男は㋑預貯金(2,000万円)を相続したい。 |
| 【ケース①】自宅の評価額が3,000万円の場合 |
|
この場合、遺産全体の評価額は、㋐自宅:3,000万円+㋑預貯金:2,000万円となりますので、5,000万円となります。 長男が㋐3,000万円の自宅を取得すれば、法定相続分から算定される上記2,500万円の取り分と比較して、500万円を多く取得することになります。 |
| 【ケース②】自宅の評価額が1,000万円の場合 |
|
一方、この場合では、遺産全体の評価額は、㋐自宅:1,000万円+㋑預貯金:2,000万円となり、3,000万円となります。 長男が㋐1,000万円の自宅を取得すれば、法定相続分から算定される上記1,500万円の取り分と比較して、500万円不足することになります。 |
遺産分割の際、不動産を評価する方法は複数あり、どの方法で評価するかによって評価額が異なるため、上記のような問題が生じがちなのです。
不動産を取得する相続人は、できる限り評価額を抑えたいと考えるでしょうし、逆に不動産を取得しない相続人はできる限り評価額を高めたいと考えることでしょう。
このように相続人間で評価額をめぐって意見が対立すると、遺産分割協議が進まない結果となります。
そのため、相続した不動産の時価を、どのような方法で、どう評価するかが重要な問題になってくるのです。
相続した不動産の評価方法 |
相続した不動産の評価方法としては、大きく分けて以下の3種類があります。
①不動産鑑定を行う |
最も適正に不動産の時価を評価する方法は、不動産鑑定士に鑑定の依頼することです。
ただし、不動産鑑定士による鑑定には、一般的に数十万円の費用を要することに注意が必要です。
この費用は、遺産の中から支出することができますが、その分だけ遺産が減ってしまいます。そのため、不動産鑑定士に依頼することを望まない相続人が出てくることも多く、相続人全員の同意が得られない可能性が高いです。
また、不動産鑑定士による鑑定結果には、法的な拘束力がありませんので、その鑑定結果に異議を唱える相続人が出てくることも少なくありません。
したがって、費用をかけて鑑定を依頼したからといって、それだけで遺産分割協議をスムーズに進めることができるとは限らないのです。
②取引価格(実勢価格)を調査する |
実務上では、不動産業者に査定を依頼することによって、市場における取引価格(実勢価格)を調査することが多いです。不動産の「時価」を評価するためには、この方法も合理的なものといえます。
ただし、査定される価格は業者ごとに異なり、バラツキが出てくることが多いです。
ひとつの業者でも、たとえば、「2500万円~2800万円」といったように、査定する価格に数百万円の幅を持たせることもあり、評価額を明確に割り出すのは意外と難しいことには注意しなければなりません。
そこで、円満な遺産分割を実現する工夫として、各相続人がそれぞれ別の不動産業者に査定を依頼し、各社の査定書を持ち寄り、それらの平均価格を評価額として合意するという方法も考えられます。
③公的に定められた評価額を参考にする |
手間をかけない評価方法として、次のような公的に定められた評価額を参考にして、評価額を割り出す方法もあります。
| 〇固定資産税評価額 |
| 〇相続税評価額 |
| 〇地価公示価格 |
ただし、これらの金額をそのまま不動産の評価額とすると、時価よりも低く見積もる可能性があるので、ご注意ください。
固定資産税評価額は、実勢価格の7割程度、相続税評価額は実勢価格の8割程度となっていることが多いです。また、土地については、実勢価格の1.1~1.2倍程度が公示価格となっていることも多いです。
実務では、固定資産税評価額を0.7で割り戻したり、相続税評価額を0.8で割り戻したりした額を不動産の評価額とすることも多いです。
遺産分割における不動産の評価方法の決め方 |
遺産分割を進めるためには、不動産の評価方法と評価額を決めなければなりません。
その取り決め方は、次のとおりとなります。
①相続人どうしで話し合う |
まずは、相続人どうしの話し合いによって、不動産の評価方法や評価額を決めます。
法律で一律に評価方法が定められているわけではありませんので、相続人全員が同意すれば、どのような方法で評価しても問題はありません。
極端にいえば、評価をせずに遺産を分けても、相続人全員の同意があれば、何の問題もありません。ただし、相続税を申告する際には、所定の方法で不動産を評価する必要があることにご注意ください。
遺産分割の実務では、まずは固定資産税評価額などを参考に評価額を割り出し、それで納得しない相続人がいる場合には、不動産業者に査定を依頼して、実勢価格を調査することが多いです。
②遺産分割調停で話し合う |
相続人どうしで話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に対し、遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割の調停では、中立・公平な調停委員会(裁判官1名と調停委員2名)を介して、話し合いを行います。
通常、2名の調停委員が、各相続人から順番に言い分を聴き取り、調整しながら話し合いを進め、合意による解決を目指していきます。
その中で不動産の評価方法についても話し合い、合意ができたら評価額を割り出したうえで、遺産の分け方の話し合いへと進みます。
不動産の評価方法の合意が得られない場合は、裁判所が指定した不動産鑑定士による鑑定を提案されることもあります。この提案に相続人全員が賛成すれば、裁判所の主導により不動産鑑定が行われます。
その後、遺産の分け方について相続人全員が合意すれば調停が成立し、合意した内容に従って、実際に遺産を分けることになります。
③遺産分割審判で決定する |
遺産分割調停で相続人全員による合意に達しない場合は、遺産分割審判の手続きに自動的に移行します。
遺産分割審判では、当事者が提出した意見や証拠を踏まえて、家庭裁判所が遺産の分け方を決めます。
不動産の評価方法についても、家庭裁判所が相当と認める方法で行い、評価額を決めます。審判まで進むと不動産鑑定が行われることも多いですが、不動産業者の査定書を参照するなどして評価額を決めるケースもあります。
|
実際に不動産の評価額を争った事例「遺言で全財産を失いそうなとき...。遺留分の請求で守れる権利と実例。」は、「こちら」をご確認ください。 |
|
調停・審判の手続きの詳細は、「遺産分割調停・審判とは?申し立て方法から流れ・期間・費用まで弁護士が詳しく解説」もご確認ください。 |
相続した不動産を分割する方法 |
不動産の評価額を適正に算定できたとしても、遺産の分割を実現するためには工夫を要することが多いです。
遺産の不動産を分割する方法としては、次の4種類があります。
| ➊現物分割 | たとえば、配偶者は自宅を取得し、長男は預貯金を取得するというように、遺産を現物のまま分ける方法。なお、土地は、分筆して分割することも可能。 |
| ❷換価分割 | 不動産を売却し、その売却代金を分割する方法。 |
| ➌代償分割 | 一部の相続人が不動産を取得し、法定相続分を超える分については、他の相続人へ代償金を支払うことで、遺産分割を実現する方法。 |
| ➍共有分割 | 不動産を相続人全員の共有とする方法。 |
➍共有分割によれば、遺産分割を容易に実現できます。しかし、不動産を共有のままにしておくと、後々のトラブルにつながりやすいため、オススメはできません。
➌換価分割の方法では、実際の売却代金を前提にして分割を行うことになるので、評価額は問題となりませんが、不動産を手放す必要があります。
遺産となった不動産を手元に残すためには、➊現物分割または➌代償分割による必要があります。
この場合には、不動産の評価に関して、相続人間で意見対立が生じやすく、適正に評価することが重要となってきます。

おわりに |
相続した不動産の評価方法は、重要な論点ですが、相続人どうしの話し合いにより、円満に遺産分割が行われるケースも少なくありません。
しかし、評価方法をめぐる対立は、単なる数字の問題だけでなく、相続人間の感情的なわだかまりが背景にあることも多く、その結果、話し合いが長期化・難航する場合があります。
こうした場合や揉めそうな気配がある場合には、早めに弁護士へご相談いただくことが大切です。
弁護士は、遺産分割協議を代理して進めるだけでなく、専門的な観点から助言や説得を行い、評価方法の決定を含めて解決への道筋を整えます。
これによって、相続人どうしでは解決が難しい問題でも、早期かつ公平な解決が期待できる可能性があります。
湊第一法律事務所では、相続問題や不動産問題に精通した弁護士が、相続全般について親身かつ丁寧なサポートを行っています。
不動産を相続し、評価方法や分割についてお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
投稿日:2025年8月20日
【この記事の監修弁護士】
 |
弁護士 嶋村 昂彦 都内大手事務所および地域密着型の事務所で培った幅広い経験を活かし、企業・個人を問わず、多様な案件に柔軟かつ丁寧に対応。 |
<略歴>
栃木県出身。早稲田大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。
都内大手法律事務所および横浜市内の法律事務所で実務経験を積む。
中小企業法務をはじめ、相続(遺産分割・遺留分・遺言書作成・相続放棄など)・成年後見業務・債務整理などの幅広い個人法務に携わる。
また、神奈川県弁護士会所属時には、犯罪被害者支援委員会に在籍し、犯罪被害者支援といった公益活動にも注力する。
現在は、湊第一法律事務所パートナー弁護士として、企業・個人の双方に対し、信頼と安心をもたらす法的支援を提供するため邁進する。
<主な取扱分野>
・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
・相続問題(遺産分割・遺留分・遺言書作成・相続放棄など)
・労働事件(労使双方)
・債権回収