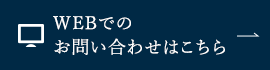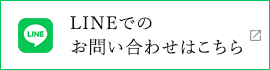「遺産分割」は、円満に終わるケースも多い一方で、親族の関係を壊してしまうほど深刻な争い(=争続)に発展してしまう悲しい話も後を絶ちません。
遺産分割の際に揉める原因の一つとして、今回テーマとする「特別受益(とくべつじゅえき)」の存在があります。

特別受益とは、被相続人(亡くなった方)が生前、特定の相続人に対して行った住宅資金の援助や事業資金の贈与、遺言による贈与(遺贈)など、相続分に影響を与える特別な利益を意味します。
被相続人が生前に特定の相続人だけを優遇していた場合、他の相続人との間に不公平感が生まれます。
そのため、 特別受益の制度は、この不公平を正して、実質的に平等な遺産分割を実現するために設けられています。具体的には、特別受益を遺産に「足し戻す」ことで、公平な分割を可能としています(民法903条1項)。
本記事では、遺産分割や遺留分、遺言書の作成など相続問題に精通する弁護士が、≪特別受益の概念から計算方法≫・≪対象になるケース・ならないケース≫・≪2023年施行の「10年ルール」≫を分かりやすく解説します。
目次
「特別受益」とは何か? |
特別受益とは、一部の相続人が、亡くなった方から生前に受けた特別な援助(生前贈与)や、遺言によって受けた特別な利益(遺贈)を意味します。
民法では、こうした特別な利益を、遺産分割の際、遺産に足し戻して計算することで、相続人どうしの公平を図る仕組みを採用しています。
この計算プロセスを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。
例えば、父が亡くなり、遺産が4000万円、相続人が長男と次男の2人のケースで考えてみましょう。そして、このケースでは、父が生前、長男にだけ事業資金として2000万円を贈与していたとします。
もし、特別受益の制度がなかった場合には、次のとおりに父の財産が分けられます。
| 長男 | 2,000万円(遺産) + 2,000万円(生前贈与) = 合計4,000万円 |
| 次男 | 2,000万円(遺産) = 合計2,000万円 |
この分割方法では、兄弟の間で父の財産から得られた利益に2000万円もの差がついてしまい、次男としては納得できないことでしょう。
そこで、「特別受益の持ち戻し」を行って、生前贈与による利益を考慮することで、公平な分割を目指すのです。
特別受益になるモノ・ならないモノ |
では、具体的にどのようなものが特別受益と判断されるのでしょうか?
まずは、実際に民法の条文を確認してみましょう。
| <民法903条1項> |
| 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 |
しかし、この条文の文言だけでは、具体的に「何が特別受益に該当する・しないか」の判断が難しいかと思います。
そこで、具体的なケースを通じて、説明を行っていきたいと思います。
ポイントは、全ての生前贈与が特別受益に該当するわけではない点、またキーワードとして、「扶養的な援助を超えるかどうか」を抑えておきましょう。
① 特別受益に該当する可能性が高いケース |
扶養する義務の範囲を明らかに超えるような、生計の基盤となるような援助が典型例です。
㋐ 生計の資本としての贈与 |
(例)
〇マイホームの購入資金や頭金の援助
〇事業の開業資金や経営難に陥った事業への資金援助
〇高額な学費(例:1人だけ私立大学医学部に進学させた場合の学費など、他の相続人と比べて著しく差がある場合)
〇特定相続人の多額の借金を肩代わりした場合
㋑ 婚姻・養子縁組のための贈与 |
(例)
〇一般的な結納金や結婚祝いの範囲を大きく超える高額な持参金や支度金
㋒ 遺贈(遺言による贈与) |
〇「長男に全財産を相続させる」・「A銀行の預金は長女に遺贈する」など遺言によって与えられた財産は、すべて特別受益となります。

② 特別受益に該当しない可能性が高いケース |
一方、親族間の助け合いとして扶養義務の範囲内と判断されるものは、特別受益に該当しません。
| 〇常識的な範囲における生活費の援助やお小遣い 〇お年玉、入学・卒業祝い、結婚祝いなどで常識的な範囲の金額 〇相続人全員が同程度の教育(例:全員が大学に進学)を受けている場合の学費 〇生命保険金(原則として、受取人固有の財産とされます。しかし、保険金額があまりに高額で不公平が著しい場合には例外的に特別受益として考慮されることもあります。この点を判断した決定として、最二小決平成16年10月29日(民集58巻7号1979頁)。) |
最終的には、家庭の経済状況や地域性、他の相続人とのバランスなどを総合的に見たうえで、特別受益に該当するか判断されます。
③ 特別受益として持ち戻さないもの |
注意点としては、仮に扶養義務の範囲を超える贈与であっても、次の場合には、特別受益として、遺産分割の際に考慮しないことがあります。
㋐ 被相続人が持戻しの免除の意思表示をした場合 |
被相続人が相続人に対し、扶養義務を超える生前贈与をしたけれども、「その贈与は遺産分割の際に持戻しの計算をしなくてよい。」という意思表示をしている場合、遺産分割の際に特別受益として考慮せずに分割を行うこととなります。
| <民法903条3項> |
| 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。 |
㋑ 婚姻期間が20年以上の夫婦において、被相続人が、他方の配偶者に対し、居住用の建物やその敷地を遺贈または贈与した場合 |
この場合には、被相続人は、その遺贈または贈与については、被相続人が持戻しを免除した意思を示したと推定され、持戻しは行いません。そのため、特別受益を考慮せず、遺産分割を行うことになります。
| <民法903条4項> |
| 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。 |
特別受益がある遺産分割のシミュレーション |
特別受益がある場合の計算は、以下の4つのステップで行います。少し複雑に感じますが、1つずつご確認いただけたらと思います。
イメージとしては「足して、引く」とお考えください。
【設例】 |
|
〇亡くなった方(被相続人):父 |
【計算ステップ】 |
▼ステップ1:みなし相続財産を算定 |
まず、被相続人が亡くなった際における現実の遺産に対し、「遺産の前渡し」である特別受益額を足し戻します(=特別受益の持ち戻し)。これを「みなし相続財産」と呼び、遺産分割における計算の土台となります。
| 6,000万円(現実の遺産) + 1,000万円(長男の特別受益) = 7,000万円(みなし相続財産) |
▼ステップ2:法定相続分で「一応の相続分」を計算 |
次に、この「みなし相続財産」を法定相続分で分けます。これはあくまで仮の取り分となります。
|
〇母(法定相続分1/2):7,000万円 × 1/2 = 3,500万円 |
▼ステップ3:特別受益者の取り分を調整 |
特別受益を受けた長男は、すでに1000万円を「前渡し」で受け取っています。そのため、ステップ2で計算した、仮の取り分からその額を引きます。
|
〇長男の最終的な取り分(具体的相続分):1,750万円(一応の相続分) – 1,000万円(特別受益額) = 750万円 |
▼ステップ4:他の相続人の最終的な取り分を確定する |
特別受益を受けていない母と長女は、ステップ2で計算した「一応の相続分」がそのまま最終的な取り分となります。
|
〇母の具体的相続分:3,500万円 |
【結論】 |
ここまでの計算によって、遺産6000万円は、母が3500万円、長男が750万円、長女が1750万円という形で分配されます。
特別受益の持ち戻しによって、不公平が是正されたことが分かるかと思います。
特別受益の評価の基準時 |
特別受益に関する計算方法と並んで重要なのが、「特別受益をいつの時点の価値で評価するのか」という問題です。
例えば、30年前に贈与された土地の価値が、今では大幅に上昇している、ということも珍しくありません。
結論として、特別受益の評価は、「相続開始時(亡くなった時)」の時価で行います。
その理由は、「贈与がなければ、その財産は遺産として残っており、相続開始時の価値で残っていたはずだ。」と考えるからです。贈与時の安い価格で計算すると、その後の価値上昇分を贈与された人だけが独り占めすることになり、かえって不公平になるためです。
したがって、贈与時に500万円だった土地が、相続開始時に3000万円に値上がりしているような場合、持ち戻しの計算では3000万円と取り扱って計算を行います。
特別受益の主張制限 |
| これまでは、特別受益に関する主張に期間の制限がありませんでした。 しかし、2023年4月1日に施行された改正民法により、状況が一変しました。 |
 |
|
【新ルール:相続開始から10年で特別受益の主張ができなくなる】 |
法改正によって、相続が開始(被相続人が亡くなった時)してから10年が経過すると、その後の遺産分割では、原則として特別受益の主張ができなくなります(民法904条の3)。
したがって、遺産分割の協議が長引いてしまい、相続開始から10年が過ぎてしまうと、これまで解説してきた特別受益に関する「持ち戻し計算」は適用されず、単純に法定相続分に応じて、遺産を分割することになります。
先ほどの例で、相続開始から10年経過後の分配がどうなるか見てみましょう。
|
〇遺産6,000万円 〇母(法定相続分1/2):3,000万円 |
長女は、相続開始から10年以内に分割していれば、1750万円を取得できていたはずが、1500万円まで減ってしまいました。逆に、生前贈与を受けていた長男の取り分は750万円から1500万円と増加しています。
このとおり、「10年」という時の経過が、相続人間の公平性をリセットしてしまうのです。このルールは、遺産分割を長期間放置させず、法律関係を早期に安定させること(特に所有者不明土地問題の解消)を目的としています。ただし、「10年以内に家庭裁判所に対し、遺産分割の調停・審判を申し立てた場合」はこのルールの対象外となります。
なお、相続開始から10年が経過した後も、相続人全員の合意で特別受益を考慮することはできると法的には考えられています。しかし、特別受益を考慮する遺産分割のケースでは、相続人どうしの意見対立が激しいと想定されるため、合意を取り付けることは現実的に難しいと思われます。
| <民法904条の2> |
| 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。 二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき |
|
【注意点】 改正された上記民法904条の2は、2023年4月1日以降に生じた相続に関して、相続開始から10年を経過した場合、特別受益の主張ができないとするものです。2023年4月1日より前に生じた相続は、その相続開始から10年または2028年3月31日の遅い時期を経過すると、特別受益の主張ができなくなります(附則(令和3・4・28法24)3条)。 |
おわりに |
遺言書の作成を考えている方へ |
生前に築いた財産は、ご家族への思いとともに引き継がれます。
その思いが争いに変わらないよう、贈与や遺贈の扱いを遺言書で明確に示すことは、残された家族への最後の心配りです。そのためには、持ち戻し免除の意思表示などを適切に記しておくことが、安心と絆を守る最善の方法となります。
文案や内容に迷う場合は、是非、弁護士にご相談ください。
相続人となられた方へ |
特別受益を主張できる期間は、相続開始から10年までと限られています。
限られた時間の中で、まずは相続人どうしで冷静に話し合い、それが難しい場合には迷わず弁護士にご相談ください。
弁護士は、法的視点と交渉経験を活かし、あなたの権利を守りながら、納得できる解決への道を共に歩みます。
相続が、家族の絆を壊す「争続」にならないために、正しい知識を武器に、迅速かつ適切な行動を心がけましょう。

投稿日:2025年8月18日
【この記事の監修弁護士】
 |
弁護士 嶋村 昂彦 都内大手事務所および地域密着型の事務所で培った幅広い経験を活かし、企業・個人を問わず、多様な案件に柔軟かつ丁寧に対応。 |
<略歴>
栃木県出身。早稲田大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。
都内大手法律事務所および横浜市内の法律事務所で実務経験を積む。
中小企業法務をはじめ、相続(遺産分割・遺留分・遺言書作成・相続放棄など)・成年後見業務・債務整理などの幅広い個人法務に携わる。
また、神奈川県弁護士会所属時には、犯罪被害者支援委員会に在籍し、犯罪被害者支援といった公益活動にも注力する。
現在は、湊第一法律事務所パートナー弁護士として、企業・個人の双方に対し、信頼と安心をもたらす法的支援を提供するため邁進する。
<主な取扱分野>
・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
・相続問題(遺産分割・遺留分・遺言書作成・相続放棄など)
・労働事件(労使双方)
・債権回収