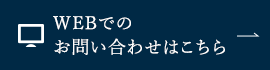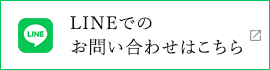| 遺言書により全遺産を特定相続人が取得。依頼者の遺留分を守り抜き、調停で早期解決を実現した事例。 |
目次
ご相談の背景 |
ご依頼者様は、被相続人(亡くなった方)の実子であり、複数いる相続人の1人でした。
しかし、被相続人が作成した遺言書には、「全財産をAのみに相続させる。」と明記されており、ご依頼者様を含む他の相続人には一切の財産が分配されない内容となっていました。
遺言書が有効である限り、その内容が優先されます。そのため、ご依頼者様は、この遺言を目にしたとき、「本当に自分には何の権利もないのか?」と強い不安と戸惑いを感じておられました。
当職は、法律相談の中で、ご依頼者様から丁寧にご事情を聴取し、遺言書が有効であっても、法定相続人には遺留分という最低限の取り分を守る権利があることを説明しました。
さらに、この権利には短い時効制限があること、そのためには迅速な対応が求められることもご理解いただきました。
遺留分侵害額請求の流れについてもご理解いただき、正式にご依頼を受けることになりました。

| <遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)とは?> |
|
遺留分侵害額請求(民法1046条1項)とは、遺言や贈与によって、相続人の最低限の取り分が侵害された場合にはその不足分に相当する金銭を請求できる権利を意味します。 たとえば、「特定の人に全財産を譲る」といった内容の遺言書が残されていると、この遺言によって財産を受け取れない配偶者や子は、自身の遺留分が侵害される結果となります。この場合、遺産を受け取った人に対して、侵害された分に相当する金銭を支払うよう請求ができます。 |
| <遺留分請求の流れ> |
| <①相手方への通知> 遺留分を請求する意思を 明確に伝える必要があります。 証拠を残すため、内容証明郵便を使用して 送付するのが一般的です。 ⇓ <②協議・調停> 話し合いで解決しなければ、 家庭裁判所に調停を申し立てます。 (調停前置主義) ⇓ <③裁判> 調停で合意に至らない場合、 裁判で判断を求めます。 |
| <遺留分請求権の時効> |
|
民法1048条によって、 |
担当弁護士の対応 |
① 課題と対応方針 |
今回の案件では、ご依頼者様が遺産全体を把握できていない状況でした。
さらに、被相続人が生前から特定相続人Aと同居していたため、遺産の一部が不明瞭であり、隠匿や生前贈与、不自然な資金移動の懸念もありました。
そこで、当職は、
| 〇遺産全体の正確な把握 〇遺留分侵害額を最大限に算定すること |
といったように、ご依頼様の適正な権利実現を目標にして、徹底した事前調査を行う方針を立てました。

② 遺留分侵害額の請求に向けた徹底調査 |
遺留分の請求では、「遺産として何があるのか」を単に列挙するだけでなく、遺産の評価・過去の贈与や特別受益の有無などを総合的に把握し、正しい「遺留分の対象となる財産額」を確定させることが重要です。
そこで、以下の調査を段階的に実施しました。
㋐ 金融機関に対する取引履歴の開示請求:預貯金口座や他の金融資産を調査するため、各金融機関に対し、10年分の取引履歴を開示請求。 |
これによって、不自然な送金や銀行口座の解約がないかを確認できます。その結果、遺言によって遺産を取得する相続人に対し、多額の送金があったり、相続人が通帳を管理していた状況で多額の出金あったりすれば、その金額を遺留分算定の対象財産に計上できる可能性があります。
㋑ 不動産の適正価格の調査:遺産に不動産が含まれていたため、固定資産税評価額だけではなく、不動産業者から複数の査定を取り、市場価格に近い「実勢価格」で評価。 |
固定資産税評価額は、通常、実勢価格よりも低額となる傾向があるため、不動産価格の評価は、多角的に実施する必要があります。
|
「相続不動産の評価」に関する詳細な解説は、「弁護士が教える|相続不動産の評価方法と分割手段の基礎」もご確認ください。 |
㋒ 生命保険金について、特別受益に該当するかの検討。 |
今回の調査の過程で、生命保険契約が確認されました。
生命保険金は、原則として、受取人固有の財産となります。しかし、保険金額が過大である場合には、「特別受益」として遺留分算定の財産に含まれる可能性があります。
| ①保険金受取人に指定された者が取得する死亡保険金は、原則として、受取人の固有の財産であり、特別受益に該当しない。 |
| ②ただし、保険金の額や遺産総額に対する比率に加え、同居の有無、介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の事情を総合考慮して、死亡保険金を特定の相続人が取得することで、著しい不公平が生じる特別な事情がある場合には、特別受益と判断される可能性がある。 |
この決定は、直接には遺産分割に関する判断のものです。したがって、遺留分の算定の場面において、必ずしも生命保険金を特別受益として加味できるわけではありませんが、場合によっては、この判断内容を使用することが可能な場合もあります。
今回の案件では、生命保険契約の内容を確認し、保険金額が多額であったこともあり、この決定に基づいて、一定額を遺留分の対象財産に加えるべきであると主張することにしました。
|
「死亡保険金は特別受益にあたるか―。固有財産である死亡保険金を守り抜いた解決事例。」は、「こちら」をご確認ください。 |
|
「特別受益」に関する詳細な解説は、「特別受益とは?計算方法・対象となるケース・10年ルールまで完全ガイド」もご確認ください。 |
③ 遺留分の金額算定と主張戦略の構築 |
以上までの徹底調査で判明した結果をもとに、遺留分の算定の基礎になる財産額の再評価を行いました。
その結果、当初の遺産額よりも評価額が高くなり、これに伴って、ご依頼者様が請求できる遺留分の請求額も増加しました。
そこで、当職は、調査結果を根拠にして、遺産調査前の状況よりも高い金額を用いて、遺留分侵害額の請求調停を家庭裁判所に申立てました。
④ 家庭裁判所での遺留分調停と解決 |
調停では、事前準備した調査資料を基にして、被相続人の遺産の全体像と遺留分額を客観的に説明しました。
数回の調停期日を経て、請求に近い金額で調停が無事に成立しました。 ご依頼者様は「権利を守ってもらえた」と大変安心され、結果として、早期解決が実現しました。

弁護士がサポートした結果 |
✅徹底調査によって正確に把握し、適正な評価を実現。
✅事前準備の甲斐あり、調停が早期に成立。
✅法的権利である 遺留分を適正な額で認めさせることに成功。
担当弁護士のコメント |
今回の案件では、表面的な主張だけを単に行うのではなく、遺留分侵害額の算定の根拠となる遺産全体の再構成と証拠資料の積み上げを丁寧に実施しました。
そして、裏付け資料の収集と精査、実勢価格の評価、特別受益の検討などを通じて、調停段階で説得力ある資料を提示しました。
調査方法と主張の工夫によって、遺留分侵害額請求の結果が大きく変わる可能性があります。
遺言によって、相続財産を受け取れない場合でも、遺留分侵害額の請求によって守れる権利があります。ただし、時効や証拠収集の限界もあるため、早期のご相談が不可欠です。
湊第一法律事務所では、遺産を徹底調査して、事前準備が重要となる遺留分侵害額の請求の案件も、依頼者の利益を最大限引き出すよう尽力しております。
同様のお悩みをお持ちの方は、ぜひお早めにご相談ください。
投稿日:2025年8月1日
更新日:2025年8月18日
【この記事の監修弁護士】
 |
弁護士 嶋村 昂彦 都内大手事務所および地域密着型の事務所で培った幅広い経験を活かし、企業・個人を問わず、多様な案件に柔軟かつ丁寧に対応。 |
<略歴>
栃木県出身。早稲田大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。
都内大手法律事務所および横浜市内の法律事務所で実務経験を積む。
中小企業法務をはじめ、相続(遺産分割・遺留分・遺言書作成・相続放棄など)・成年後見業務・債務整理などの幅広い個人法務に携わる。
また、神奈川県弁護士会所属時には、犯罪被害者支援委員会に在籍し、犯罪被害者支援といった公益活動にも注力する。
現在は、湊第一法律事務所パートナー弁護士として、企業・個人の双方に対し、信頼と安心をもたらす法的支援を提供するため邁進する。
<主な取扱分野>
・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
・相続問題(遺産分割・遺留分・遺言書作成・相続放棄など)
・労働事件(労使双方)
・債権回収