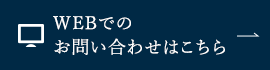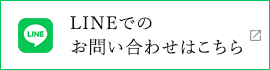近年、デジタル化の流れに伴い、企業間取引や個人間の契約において、「電子契約書」が急速に普及しつつあります。
契約書の電子化は、紙媒体の契約書に代わる方法として広まりつつあり、法的効力や証拠力についても制度的な裏付けが整備されています。
しかし、紙媒体の契約書に慣れ親しんだ方の中には、「電子契約書は本当に法的な効力があるのか?」・「紙の契約書と比べてどんなメリットがあるのか?」と疑問に感じる方も少なくありません。
そこで、本記事では、上場企業のインハウスローヤーとして、年間で数百を超える各種契約書の作成・レビューを行い、企業法務の最前線で活躍している弁護士が、≪電子契約書のメリット≫や≪電子契約の法的効力≫、≪電子署名法≫などについて、解説します。 目次
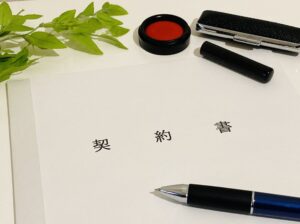
紙媒体の契約書における課題 |
従来の紙媒体の契約書には、複数の課題が内在していました。
まず、物理的な保管スペースの確保が企業の大きな負担となります。特に、長期間の保存が義務付けられている国税関係帳簿書類(最長7年間)では、その負担が顕著でした。
また、契約締結のプロセスにおいても、郵送や対面でのやり取りに起因する時間的コストや郵送費・交通費が発生し、迅速に行われるべき業務のボトルネックとなっていました。
さらに、契約金額に応じて課税される印紙税は、特に高額な取引や多数の契約を扱う企業にとって、無視できない財務上の負担でした。

電子契約の実務上のメリット |
電子契約の導入には、主に以下のようなメリットが挙げられます。
【メリット1】 コスト削減 |
・紙媒体の契約書では必要だった郵送代、封筒代、印刷代、人件費、保管費用などが不要となり、契約コストを削減できます。
・印紙税法上、電子契約書は課税文書(同法2条)に該当しないため、印紙税がかかりません。そのため、収入印紙は不要です(国税庁『取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い』参照)。
【メリット2】業務の効率化・スピードアップ |
・契約締結までのプロセス(印刷、押印、郵送、返送など)が不要となり、遠隔地間でも迅速に契約が締結できます。
・オンライン上で電子署名を行うことで、最短で当日中に契約締結が可能です。
・契約書の検索や管理が容易になり、文書管理の効率化も図れます。
【メリット3】コンプライアンス・ガバナンスの強化 |
・電子契約は原本の紛失や劣化のリスクが低く、電子署名やタイムスタンプの活用によって、改ざんリスクを低減できます。
・契約締結の履歴(誰が、いつ、どの契約書に署名したか)が正確に記録され、内部統制や監査の効率化に寄与します。
・契約情報や締結進捗の可視化により、ガバナンスの強化が図れます。
【メリット4】 保管・管理の容易さ |
・電子データとして契約書を保存できるため、物理的な保管場所が不要となり、関係者間での共有も容易です。
・電子契約書は、原本とコピーが同等の価値を持ち、遠隔地へのバックアップも可能です。
【メリット5】非対面・リモート対応 |
・テレワークやオンライン面談の普及に伴い、非対面での契約締結が可能となり、出社や対面の必要がなくなります。
【メリット6】法令対応・電子交付の拡大 |
・多くの契約類型で電子化が認められるようになり、法令に基づく電子交付も可能となっています。
【メリット7】 取引先にもメリット |
・印紙代や郵送費などのコスト削減効果は取引先にも及び、双方にとってメリットがあります。
・取引が反復的な場合、契約締結までのスピードアップの恩恵も大きくなります。
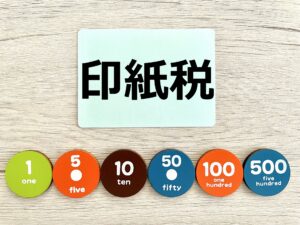
電子契約書の法的効力 |
【原則】 |
結論からいうと、電子契約書は、原則として、紙の契約書と同じく法的な効力を持っています。
そもそも、我が国における契約は、一部の例外を除き、当事者双方の合意によって成立するため、書面であるか否かは、法的効力に影響しません。
【例外】 |
ただし、消費者保護や紛争予防といった特定の目的のため、一部の契約は、法令により書面での作成や交付が義務付けられています。
これらの契約は、現在も電子契約の対象外とされています。
公正証書による作成が義務付けられる契約 |
公正証書は、2025年9月現在、書面での作成が義務付けられており、電子化できません。
これに該当する主な契約は、以下のとおりです。
| ・任意後見人契約(任意後見契約に関する法律第3条) |
|
・事業用定期借地契約(借地借家法第23条第3項) |
|
・企業担保権の設定または変更を目的とする契約(企業担保法第3条) |
書面での作成・交付が義務付けられる契約 |
農地または採草放牧地の賃貸借契約(農地法第21条)は、公正証書は不要ですが、書面の作成が義務付けられています。
また、訪問販売などの「特定商取引に関する法律」に定められた契約書面や概要書面は、2023年6月以前は紙での交付が原則でした(同法4条1項)。もっとも、法改正により消費者の承諾があれば電子化が可能となりました(同法4条2項)。この電子交付には、印刷可能性、改変確認措置、ダウンロード通知といった要件を満たす必要があります(消費者庁『契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン』)。
以上までの例外を除き、多くの契約は電子契約で問題なく締結できます。
なお、将来的に公正証書も電子化されることになり(令和7年10月1日施行。法務省『公正証書に係る一連の手続のデジタル化の概要』)、現在の電子化できない契約の多くも対象となる可能性を秘めていると考えられます。
電子契約の信頼性を担保する技術 |
法的効力があるとはいえ、電子契約書の「改ざん」や「なりすまし」は大きな懸案事項となります。
このリスクを最小限に抑え、信頼性を担保するために、以下の技術が活用されています。これらを用いることで、電子契約は高い証拠力を持つことが可能です。
電子署名 |
電子文書が本人の意思で作成・承認されたことを証明する技術です。紙媒体の契約書における押印や署名に相当します。
タイムスタンプ |
電子文書が、特定の時刻に確かに存在し、それ以降、改ざんされていないことを証明する技術です。これによって、契約締結後の不正な変更を防ぎます。
電子署名法について |
電子署名の法的有効性を定めているのが「電子署名及び認証業務に関する法律」(通称:電子署名法)です。
この法律は、適正な手続で付与された電子署名には、紙の契約書における署名や押印と同等の法的効力があると定めています。
電子署名法には、電子契約の法的効力を論じるうえで特に重要な規定が2つあります。
第2条(電子署名の定義) |
電子署名を①「電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること(本人性)」と②「当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること(非改ざん性)」という2つの要件を満たすものと定義しています。
電子文書の「真正性」(Authenticity)という概念を、技術的に検証可能な「本人性」と「非改ざん性」という2つの要素に分解し、法的要件として明確に定めたものとなります。
第3条(真正性の推定) |
「本人による一定の条件を満たす電子署名」がなされた電磁的記録は、「真正に成立したものと推定」されると定めています。
この「推定効」は、民事訴訟法第228条第4項に基づく、紙の文書に手書きの署名や押印がある場合の「真正性の推定」に匹敵する強力な法的効果です。
裁判で電子契約の有効性が争われた際、電子署名が付与されているだけで、その文書が本人の意思に基づいて作成されたと法律上推定されることを意味し、文書の成立の真正性を否定する側の当事者に立証責任を転換させる効果をもたらします。
これによって、電子契約は紙の契約書に劣らない、場合によってはより強固な証拠力を持つ可能性が示唆されます。
電子契約書の裁判での扱い |
電子署名が付与された電子契約書は、紙媒体の契約書への署名押印と同等の証拠価値を持つため、裁判においても有力な証拠となります。
ただし、契約の相手方が電子契約に対応できるか、社内規則上の制約がないか、本人確認や権限確認(代理権など)が適切に行われているかについては、実務上の留意が必要です。
弁護士からのアドバイス |
電子契約は便利ですが、導入には次のような注意が必要です。
| 契約内容の確認 | 紙の契約書と同様、契約内容を十分に理解してから署名することが重要です。 |
| 相手方の合意 | 相手方が電子契約に同意していることを確認しましょう。 |
| 信頼できるサービスの利用 | セキュリティや法的要件を満たしている電子契約サービスを利用することが、トラブル回避の鍵となります。 |
まとめ |
電子契約は、法律上も有効であり、セキュリティ技術によって高い信頼性を確保できます。
適切なサービスを利用し、契約内容をしっかり確認することで、業務効率を向上させ、より安全な契約締結が可能となります。
このように電子契約は、コスト削減や業務効率化の観点からも大きなメリットがあります。ただし、契約内容や取引の相手方によっては注意すべき点もあります。
導入に際して不安がある場合は、弁護士にご相談いただくことで、自社の実情に合った適切な導入方法やリスク管理が可能となります。
湊第一法律事務所では、企業の皆さまの契約実務を幅広くサポートしており、電子契約の導入や運用体制の整備についても、豊富な知見を有しています。
「電子契約に切り替えたいが不安がある。」・「どの範囲まで電子化できるのか知りたい。」といったご相談にも丁寧に対応いたします。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

投稿日:2025年9月2日
【この記事の監修弁護士】
 |
弁護士 佐藤 駿介 依頼者一人ひとりに真摯に向き合い、丁寧かつ的確な対応で信頼を集める弁護士。 |
<略歴>
埼玉県出身。早稲田大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)に在学中、司法試験予備試験に合格し、続けて司法試験にも合格。
エンタメ系上場企業の法務部にて企業内弁護士として勤務し、契約書レビューや労働法務、社内コンプライアンス体制の整備など企業法務全般を担当。また、都内大手法律事務所に所属していた時期から、企業法務に加えて、離婚・不貞などの男女問題や不動産に関する法的トラブルにも数多く携わる。
現在は、湊第一法律事務所の代表弁護士として、企業・個人問わず法的支援を提供するほか、自ら設立した法人の取締役も務めるなど、実務と経営の双方に精通している。
<主な取扱分野>
・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
・債権回収
・男女問題(離婚・不貞慰謝料など)
・不動産トラブル(賃料問題・建物明渡し・不動産売買に関する紛争など)